近年、ギャンブル依存症が社会問題として深刻化しており、特にオンラインギャンブルや投資のギャンブル性が懸念されています。
依存症は単なる意思の弱さではなく、心理的・社会的要因が絡む複雑な問題です。
 編集長
編集長その解決策を探るため、都留文科大学の早野教授にお話を伺いました。
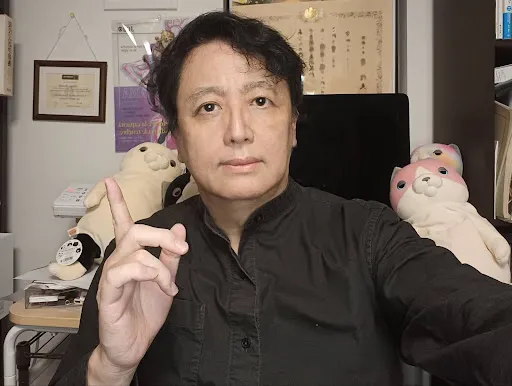
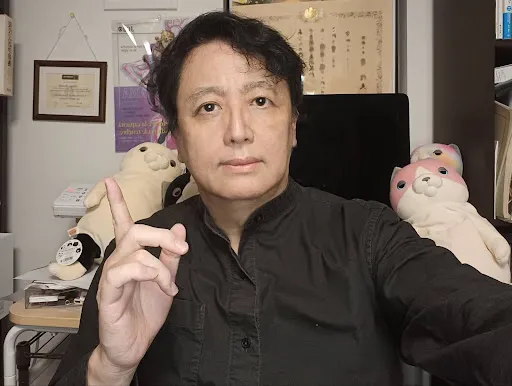
早野 慎吾
都留文科大学 大学院文学研究科 教授
専門は社会心理学、言語心理学。現在、3つの科学研究費研究に参加して、感情表現ができるAIロボットの開発を行っている。著書:『社会学から見たギャンブル依存症:そんなにパチンコがわるいのか』(ぎょうせい:近日発行予定)、『パチンコ広告のあおり表現の研究:パチンコ問題を考える』(立川言語文化研究会)など多数。
研究論文:The study of differences by region and type of gambling on the degree of gambling addiction in Japan. Scientific Reports. 2021. A Study on Effective of Gambling Advertising Expression on Gambling Addiction in Japan. Ars Linguistica. 2022など多数。
本記事では、依存症の判断基準や予防策、デジタル環境が与える影響について解説します。
これから投資に取り組む上で、依存リスクの理解を深め、健全な投資・娯楽との向き合い方を理解しておきましょう。
ギャンブル依存症とは何か?



まず、ギャンブル依存症の定義についてご教示いただけたら幸いです。



一般的にギャンブル依存症は、ギャンブル行動の制御ができなくなり、日常生活や人間関係に深刻な影響を及ぼす精神疾患と説明されます。基準としては、世界保健機構(WHO)のICD-11やアメリカ精神医学会(APA)のDSM-5などがあり、測定には、PGSI(Problem Gambling Severity Index)やSOGS(South Oaks Gambling Screen)などの簡易テストが使われています。



ただし、社会的要因や個人事情などが介入するので、一般に考えられている病気とはやや違います。たとえばインフルエンザに感染して39度の熱が出れば、誰でも罹患(りかん)と判断されます。しかし、ギャンブルに費やす時間とお金が同程度であっても、収入が少なくて深刻な状況になれば依存症で、収入が多く、支障がなければ判断が変わります。



自分自身が「依存症状態」に陥っているかどうかを判断するためのサインはありますか?



まず、簡単にできるPGSIやSOGSを使って判定するといいでしょう。自分は大丈夫と都合良く思っている人ほど危険なので、SOGSで5点以上、PGSIで8点以上であれば保健所などに相談してみるといいと思います。ギャンブルの負けをギャンブルで取り返そうと考え出したら危険なサインです。
依存症予防のための社会的取り組み



依存症予防のために、社会で行われている取り組みにはどんなものがありますか?企業によるものに限らず、政策、教育面の視点からでも差し支えございません。



政策では、ギャンブル等依存対策基本法の成立が大きいと思います。これにより、国や地方自治体(いわゆる行政)の対策が義務化され、各自治体で専門医療機関の指定や相談窓口の開設が行われました。次に、ギャンブル広告宣伝規制がありますが、公営ギャンブルや宝くじなど、どこを規制しているのかわからない状況で、この規制に関してはあまり期待できません。特に、公営ギャンブルのオンライン広告はひどいものです。



教育面では、文部科学省が「ギャンブル等依存症指導参考資料」を作成しており、小中高において依存症予防教育を実施しています。ただし、依存症の知識をもった教員はほとんどいないのですから、効果は疑問があります。効果を上げるためには、大学の教職科目に依存症教育を導入する必要があります。ゲームなどを含むオンライン環境でのリスク管理教育が重要ですが、教育が追いついていない印象を受けます。



教育現場での対策に課題があるのですね。オンライン環境のリスク管理教育として、具体的にどのような対応が必要だとお考えですか?



企業としては、有識者を呼んで研修を行うのが一般的な対応です。私が望んでいるのが金融機関の対策です。まず、ギャンブルサイトでのクレジットカード決算を禁止して、ギャンブル関連の取引をブロックするオプションを提供する必要があります。さらに、消費者金融は、ギャンブル依存症の人への貸付を制限する。IT企業の果たす役割も多々あります。ギャンブル系アプリのプレイ時間を制限できる機能設定や、AIによるターゲティング制御などはIT企業の役割です。社会全体が一致団結して対策しないと、オンラインギャンブル(特にカジノ)の対策はザル状態になります。
仮想通貨やFXの依存性について



仮想通貨やFXにのめり込む人々について、先生のご意見を聞かせてください。彼らには、どのような心理的特徴が見られるのでしょうか?



投資のギャンブル性についても調査を進めていますが、仮想通貨やFXでもギャンブル依存と酷似した状況が観察できます。仮想通貨やFXは価格変動が激しく、短期間で大きな利益を得ることが可能なので、一攫千金を狙う人が必ずいます。これは、ギャンブルの説明に使われる「射幸心をあおる」心理と同じです。



ギャンブル依存は、勝った経験(報酬効果)で説明されることが多いのですが、実際は、行動経済学で説明される損失回避の法則の方が重要です。これは、リスクを伴う行動選択を説明するプロスペクト理論に基づくもので、「損失の痛みは利益の喜びの約2倍に相当する」とされています。損失を出すと、その補填に不合理な行動をとりやすくなるのです。ギャンブルの負けをギャンブルで取り返そうと考え出したら危険というのは、このことです。さらに、元手以上に取引ができるレバレッジは危険性を増大させています。



上記の人々のように短期で大きな利益を得ようとする心理は、ギャンブル依存症とどのように関連していますか?健全な投資行動と、依存症的な投資行動の違いについても、ご教示いただけたら幸いです。



仮想通貨やFXは法的にはギャンブルではありませんが、ギャンブル性(=リスク)があり、当然のことながら短期投資ほどギャンブル性は強くなります。私の調査でも、リスクを意識する人ほど長期投資を選択する傾向が確認できます。2023年度に実施した15,000人調査では、長期投資群の平均SOGSスコアは1.22で、短期投資群は2.26でした(5点以上で依存症の疑いあり)。そしてオンラインカジノが6.09、オートレースが3.89、パチンコが2.57でした。短期投資群はパチンコに近い依存性があることがわかります。
デジタル環境と依存症リスク



デジタル技術の進化が、依存症リスクを高める要因になっていると思いますか?つまり、仮想通貨市場の24時間取引、及びSNSでの情報拡散などが、投資行動に与える依存度を助長する要因になっていると考えられますか?



オンラインで24時間取引可能な状況は、依存性をかなり高めます。ギャンブル依存を引き起こす要因に参加労力(アクセスモード)があります。現地でしか参加できないパチンコなどに比べて、オンラインでの参加労力はほぼゼロです。現金を使わないデジタルマネーは金銭使用の感覚を希薄にさせます。これらの要素は、依存性を高めます。



私の調査から、依存性の高い人ほど宣伝広告に流されやすいことがわかっています。SNSなどによる情報はガセ情報も多く、インフルエンサーがポンプ&ダンプを行うこともあります。「必ず儲かる」などの投稿やインフルエンサーのあおりなどは、冷静に考えれば裏があることがわかりますが、損失回避の心理からか、依存性の高い人はそれらの情報に流されやすい状況にあります。
健全な投資のための自己管理法



仮想通貨やFXを健全に楽しむために、どのような自己管理方法やメンタルケアが効果的でしょうか?



仮想通貨やFXには、さまざまなリスクが存在します。いろいろなところで対処方法が解説されていると思います。しかし「わかっちゃいるけどやめられない」のが依存症です。仮想通貨やFXに限らず、ギャンブルにも言えるのですが、まず投資やギャンブルをする前に、やっていい性格かやってはいけない性格かを冷静に判断することです。ギャンブル等依存症対策の根本がここにあると思います。仮にやってみて損失が出たときにリスクの高い選択をしたり、感情的になってしまう人は、向いていないと判断してください。損失が大きくなるほどのめり込んでいきます。まずは、自らの性格や気質を把握することが大切です。
最後に
本インタビューを通じて、投資とギャンブルの境界線の曖昧さと、デジタル環境が依存症リスクを高める可能性について理解を深めることができました。
健全な投資を続けるためには、自分自身の性格や行動パターンを理解し、適切な自己管理を行うことが不可欠です。
依存症の兆候を感じたら、早めに専門機関に相談することをお勧めします。
当サイトについて
当サイトBITNAVI(ビットナビ)は、仮想通貨や海外取引所について発信している総合情報メディアです。
仮想通貨FX歴5年以上のプロトレーダーが、海外で話題の仮想通貨や、おすすめの海外仮想通貨取引所を紹介しています。
中でも「仮想通貨海外取引所おすすめ比較ランキング」は人気の記事ですので、気になる方はぜひ参考にしてください。
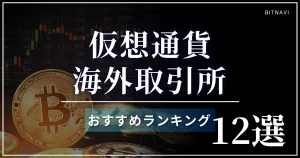
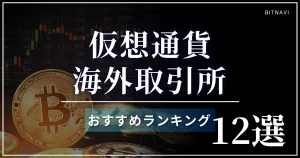
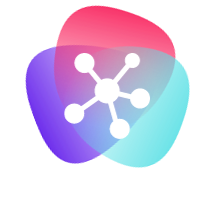
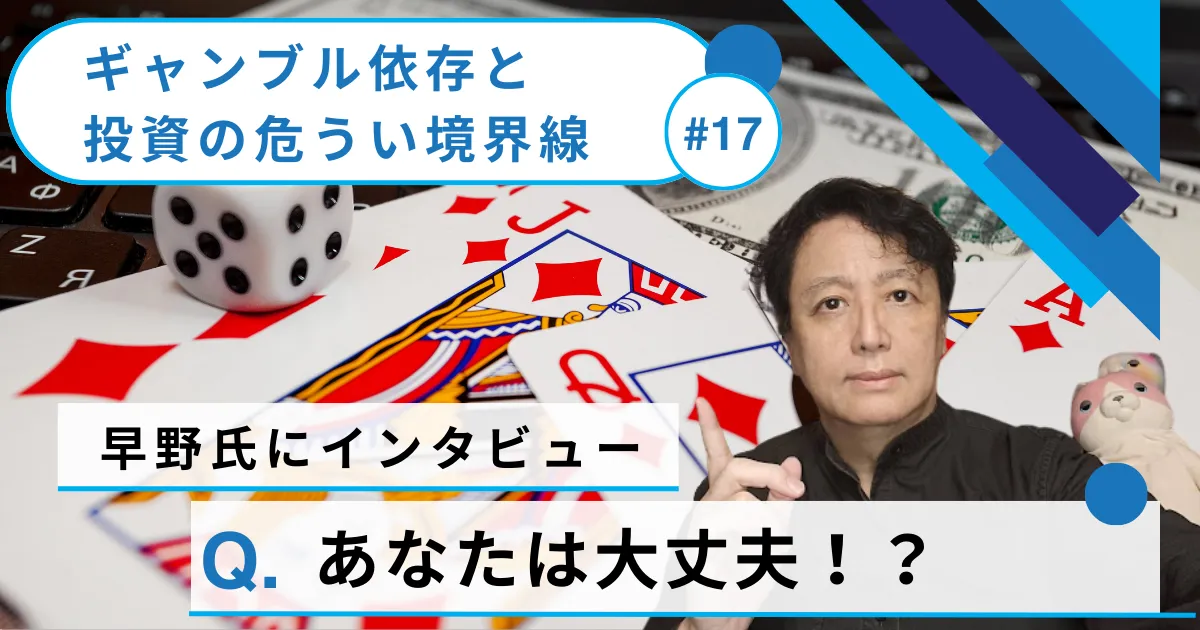

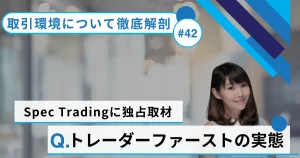

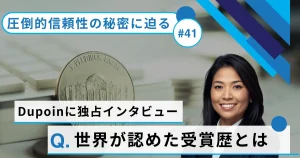

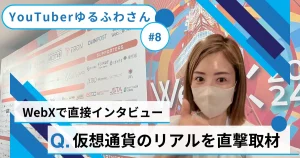
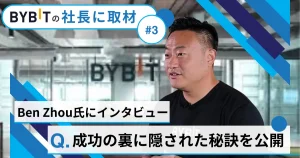
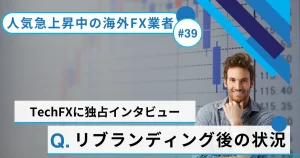
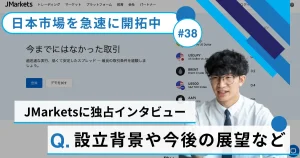
コメント