近年、仮想通貨やブロックチェーン技術の台頭により、銀行などの金融機関の存在意義や、中央銀行の役割に変化が求められています。
このような金融の転換期における課題と展望について、駒澤大学の代田先生にお話を伺いました。

代田 純
駒澤大学 経済学部 商学科 教授
1957年生。中央大大学院博士課程中退。博士(商学)。1991年日本証券経済研究所大阪研究所研究員。1994年立命館大学国際関係学部助教授を経て2002年より現職。駒澤大学で経済学部長、副学長を歴任。 近著に、『入門銀行論』(有斐閣、2023年、編著)、『デジタル化する証券市場』(金融財政事情研究会、2023年、共編著)など。2025年4月より在フィンランド、ユバスキュラ大学客員研究員。
仮想通貨と中央銀行デジタル通貨(CBDC)の位置づけ、金融商品としての制度対応、そして個人が金融とどう向き合うべきかといった幅広い視点を学ぶことができます。
この記事を読むことで、デジタル時代における金融の未来像を理解し、自身の金融リテラシーを高める一助となるでしょう。
仮想通貨で銀行の仲介機能は不要になるのか?
 BITNAVI編集部
BITNAVI編集部仮想通貨が個人間で直接送金できる仕組みを提供する中で、”仲介機能”としての銀行の必要性は今後どうなっていくとお考えでしょうか?



仮想通貨(暗号資産)はブロックチェーン技術により、分散型台帳を参加者が共有するというコンセプトです。このため、仲介者が不要になる。原理的には、そうなるのですが、仮想通貨が個人間での支払手段として普及するまで、まだしばらく時間がかかるでしょう。現状では支払手段としてよりも、投資資産として注目されている。



今まで日本では、仮想通貨を資金決済法で対応してきました。しかし、最近、金融庁は金融商品取引法(以下、金商法)により、金融商品として暗号資産を位置づけようとしている。これが仮想通貨に対する規制強化になるのか、緩和なのか、現状では評価が難しい。米国では、バイデン政権下で、仮想通貨を連邦証券法で規制しようとして、業界から反発が強まりました。しかし、トランプ政権となって、風向きが変わり、規制緩和に向かっています。



また現行の金商法でも仮想通貨が位置づけられていないわけではありません。現行の金商法では、金融商品を主として、①有価証券、②有価証券表示権利、③電子記録移転権利、④みなし有価証券、という4つのカテゴリーから構成している。①有価証券は、国債等で券面が発行される場合です。②有価証券表示権利は、国債等で券面が発行されない場合でも、権利(利払い等)を有価証券としている。有価証券のペーパーレス化が進み、券面が発行されないことが多くなっており、こうした事態に対応している。③電子記録移転権利は、ブロックチェーンなどの分散型台帳技術(DLT)によって電子的に記録される暗号資産(仮想通貨)に関係している。④みなし有価証券は、有価証券の権利ではなくとも、有価証券とみなすもので、信託の受益権等が該当します。①~③については、投資対象となるうえ、流通性があり、売買が活発になされるという特徴があります。④については、投資対象とはなるが、流通性に乏しい。ただ、以上のように、現行の金商法でも、仮想通貨関係が取り扱われていないわけではなく、これとの関係も今後議論されるでしょう。



銀行の仲介機能も将来的には弱まっていく方向だと思いますが、まだ時間がかかるでしょう。また、仮想通貨により、金融業の仲介機能が低下する、あるいは不要になるという可能性は銀行に限った話ではありません。証券投資に関しても、投資家がDLTで参加することにより、証券取引所等の市場インフラが不要になるという可能性が指摘されています。これに伴い、各種の手数料も低下するかもしれません。しかし、いずれにせよ、まだ時間がかかるでしょう。
CBDCと民間仮想通貨の役割分担と日本における導入見通し



中央銀行デジタル通貨(CBDC)の議論が進んでいますが、それは民間発の仮想通貨とどのように役割を分けていくことになると見ていますか?日本における導入の現実味も含めて教えてください。



トランプ政権が成立する前の時点では、日米欧のスタンスを比較すると、欧州が最も積極的で、米が欧州に準じており、日本が最も消極的という印象です。日本銀行(以下、日銀)はCBDCを発行することは決まっていない、と繰り返し表明しています。



欧州中央銀行(以下、ECB)はマネーロンダリング対策もあって、CBDCには比較的積極的という印象です。先ほどもお話したように、フィンランドも含めて、欧州、あるいはユーロ圏はマネロンをかなり重視しているし、重視せざるをえない状況です。ロシア等の問題です。ユーロ参加国のなかには、キプロスのように、ロシアと経済関係が強い国が含まれています。キプロスは宗教上、文化上でロシアと歴史的にも関係が強く、ロシアとかなり経済取引があります。キプロスがギリシャの経済危機に伴って、やはり危機に瀕した前後で、ビットコイン価格が急騰したことがあります。ロシアの関与が指摘されています。現金は原則として匿名ですが、CBDCは制度設計により中央銀行が取引者を特定できるので、マネロン対策として期待されている面があります。しかし他方で、個人のプライバシーとの関係があり、人権問題でもあります。欧州は人権や環境問題を重視していますので、バランスが悩ましい問題です。



米国はトランプ政権となり、CBDCにはかなり批判的です。トランプ大統領のパウエルFRB議長に関する発言を見ても、そもそもFRBや中央銀行に、何かを託す、という姿勢も疑問視されます。他方で、民間の仮想通貨は、トランプ系を含めて、育成するのではないでしょうか。仮想通貨は、ビットコインのような価格変動が激しいものと、ステーブルコインに分かれます。ステーブルコインは、言葉としては安定しているはずですが、他の仮想通貨を担保にしているもの(価格変動が大きい)や、ドルなど法定通貨を担保にするもの(価格は安定)に分かれます。法定通貨を担保とするステーブルコインは、日本でも一般の投資対象として解禁してもよいのではないでしょうか。



他方、CBDCは制度設計により、金融政策にかなり影響を与える可能性があります。一例としては、民間銀行預金とCBDCの競合という問題があります。仮に、民間銀行預金金利が0.1%で、CBDCの金利が0.5%なら、民間銀行預金が激減して、CBDCに流入します。マネーストックに影響しますから、金融政策への影響は甚大です。日銀は、欧米の動きを見てから、になるでしょう。
ブロックチェーン技術と金融の”信用”の本質



たとえブロックチェーン技術によって”形としての銀行”が変わっても、先生が語る”信用”の本質的な役割は今後も残るのでしょうか?



指摘したように、DXやAIは待ったなしで、地域金融機関を含み、取り組む課題となっています。しかし、ブロックチェーン技術(DLT)が銀行に影響を与えるのは、まず仮想通貨が金融商品として地位を認められてから、でしょうか。イメージとしては、NISA(日本版個人貯蓄勘定)のように、銀行の口座で個人が投資信託に積み立てる、という状態です。もっとも、米国では仮想通貨(暗号資産)のETF(上場投資信託)がかなり普及しつつあります。今後、日本でも暗号資産ETFが金融商品として認可されて、NISAで売買可能となれば、状況は変わるでしょう。



しかし、M&A関係で数百億円を銀行が貸し出す際には、先ほども述べたように、社長の人柄等を十分に審査する必要があります。人を見て貸す、という信用の根幹は存続するでしょう。
デジタル時代の金融との向き合い方



通貨や銀行のあり方が変化する中で、個人が金融とどう向き合うべきか。今の時代に金融に関心を持つ人たちへ、どのような視点を持ってほしいとお考えでしょうか?



確認できないことは信用するな、でしょうか。今日、どこの国でも、スマホは生活インフラとなり、SNS等の情報は社会的に影響が極めて大きくなっています。金融に限らず、社会生活全般に言えることですが、SNS等の情報が金融システムを動揺させる事態が起こっています。米国では、スマホ証券がかなり普及し、証券口座への資金の出し入れも、スマホ銀行で可能になっています。しかも、証券取引の委託手数料の無料化がかなり進んでいます。こうした状況で、ミーム株(人気株)の売買が、SNSの情報によって大きく左右され、スマホ証券会社が決済に支障をきたす事態が生まれました。投資した本人も、もちろん損失を抱えるリスクがあります。SNS等の情報を鵜呑みにすることは、慎んでもらいたいです。
まとめ:金融のデジタル革命と私たちの未来
本インタビューでは、駒澤大学の代田純教授に、仮想通貨やCBDCが従来の金融システムに与える影響について詳しく解説していただきました。
仮想通貨とブロックチェーン技術は原理的には「仲介者不要」の金融システムを実現する可能性を秘めていますが、実用化にはまだ時間がかかるという見方が示されました。また、CBDCについては各国・地域で対応が分かれており、日本は比較的慎重な姿勢を取っていることが分かります。
一方で、金融における「人を見て貸す」という信用の根幹は、テクノロジーが進化しても存続するという洞察は特に重要です。デジタル化が進む現代だからこそ、情報の真偽を見極める目を養い、SNSなどの情報を鵜呑みにしない姿勢が求められています。
今回のインタビューが、読者の皆様のデジタル時代における金融リテラシー向上の一助となれば幸いです。
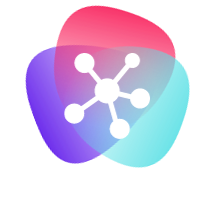


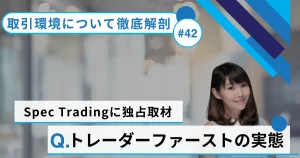

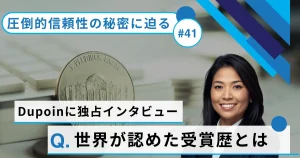

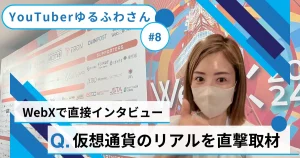
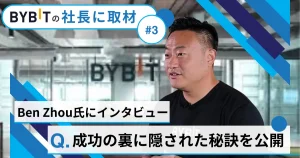
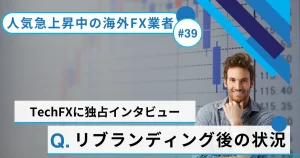
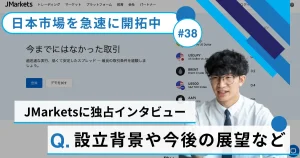
コメント