2025年に入ってから、仮想通貨市場は大きな動きを見せています。特にビットコイン価格の高騰により、短期的な投資に注目が集まっています。
しかし投資において、短期的な利益を追うだけでなく、長期的な視点を持つことも重要です。市場の変動が激しい中で、将来に備えるためにはどのような戦略が必要なのでしょうか?
そこで今回は、東京経済大学の石田成則教授にお話を伺い、仮想通貨投資を含めた長期投資のリスク管理や成功のポイントについて詳しく解説していただきました。

石田 成則
東京経済大学 教授
1991年慶応義塾大学大学院商学研究科博士課程修了後、1991年~2015年まで山口大学経済学部の助教授と教授を経て、2015年から関西大学政策創造学部教授。2025年4月より現職。2009年3月に早稲田大学にて商学博士を取得。所属学会は、日本保険学会(前理事長)、生活経済学会(理事)、日本年金学会、日本労務学会、日本ディスクロージャー研究学会など。
仮想通貨は長期投資の対象として有効か?
 BITNAVI編集部
BITNAVI編集部石田先生、仮想通貨は短期的な投資として注目されることが多いですが、長期投資の対象としても有効なのでしょうか?



仮想通貨や暗号通貨が資産保有手段として有望なことは確かです。本来は通貨として利用することになりますが、株式投資などと比較しても値動きが大きい分、投資の妙味があります。



法定通貨ではないことに不安を感じる投資家も多いと思いますが、その点はどうでしょうか?



法定通貨でないことに不安を抱く向きもありますが、通貨価値はあくまでも相対的なものであり、ひとつの国の通貨危機が他国に波及することもあり得るのです。財政赤字が大きく国債残高が多い国などは危険性が高いですね。その意味で勃興期のリスクはありますが、現在のように仮想通貨を扱う取引所が安定的に運用されるようになれば、かえって法定通貨でないことのメリットも大きくなります。



仮想通貨のメリットとしては、他にどのような点がありますか?



何より多くの仮想通貨が24時間365日間に取引可能なのは利便性が高いですし、割高な海外送金も短期間で安価に利用できることになります。ただし仮想通貨の価値が安定的であるためには、取引所がしっかりしていないといけません。一定の規制はありますが、投資家が的確に監視できる仕組みづくりが今後の課題に思えます。デジタル通貨だけにハッキングのリスクもあるので、安全対策は欠かせません。



税制面での注意点はありますか?



資産として注意すべき点は、その税制上の取扱いにあります。株式や債券の運用収益は一律20%の分離課税ですが、仮想通貨の運用収益への課税はこれより多くなります。それはこうした運用収益が雑所得に区分されてしまい、累進税率が適用され、儲けの額が大きくなるほど高い税率が適用され、それが50%近くなるケースも出てくるからです。
仮想通貨の資産としてのリスクと展望



仮想通貨に特有のリスクとしては、どのようなものがありますか?



仮想通貨・暗号通貨のリスクも、この点に関連しており、現物や実物の資産に裏付けられていないことに不安感が付きまといます。債券にしても株式にしても、国有や民間のインフラなどの資産や会社業績等の実態と関連して値動きします。もちろん投資家の思惑で値動きすることも、ままありますが、あくまでも基準となるのは実物現物の有形資産や会社業績等の無形資産の価値づけです。



そうした裏付けがないことで生じる問題は何でしょうか?



こうした裏付けをもたないために、富裕資産ではなく、浮遊資産、つまり地に足が付いていない資産と見なされてしまうのです。そのために、価値・価格の変動が読みにくく、大儲けする一方で、大損のリスクが指摘されてしまいます。



しかし最近は仮想通貨の利用も拡大していますが、それによる変化はありますか?



しかし、仮想通貨の変動が投資家の思惑だけで動く状況は変化していると思われます。その利便性から通貨としての価値が高まり、決済ができる店舗などが拡大していけば、長期のトレンドとして見れば有望な資産になるのです。今後は、こうしたトレンドの読み方や過去の値動きからその価値変動を読み解くことができる手法も精緻化していくので、より安定的な長期資産に変貌していくと考えられます。
長期投資のポートフォリオにiDeCoやNISAを活用するポイント



長期投資において、iDeCoやNISAなどの制度を活用することも重要だと思いますが、そのポイントを教えていただけますか?



長期投資に適した投資対象としては、iDeCoやNISAがあります。実は、確定拠出年金(DCプラン)は2001年10月から導入されました。加入者である従業員が毎月拠出する掛金額を決め、その積立金を加入者が自己責任で運用して運用収益を得て老後に掛金総額と併せて受給する仕組みです。そのため、受給金額は運用成績によって変動し、運用に失敗してその金額が減るのは加入者自身の責任になります。



確定拠出年金が導入された背景には、どのような社会的変化があったのでしょうか?



中小企業だけでなく大企業の社員・従業員の離転職も一般的になり、また非正規雇用者を中心に職場を渡り歩く流動労働者層も増えてきました。従来型の確定給付型年金(DBプラン)の年金給付算定方式では算定基礎となる給料として最終賃金が用いられるケースも多く、中途転職者ではこの金額は低いために老後の年金額も過少になっていました。



そうした働き方の変化に対して、確定拠出年金はどのようなメリットがあるのですか?



つまり、終身ないし長期雇用を前提としたDBプランでは短期転職者は不利になってしまうのです。これに対して、DCプランであれば個人口座に事業主による掛金と運用収益が積立てられるので、預貯金と同様に老後資産を蓄積していく感覚です。短期転職者は個人口座の資産をつぎの職場のDCプランや個人型確定拠出年金に移管することができるので、長期勤続者に比べても不利になりません。
確定拠出年金の運用において重要なポイント



確定拠出年金を運用する際に、どのような点に注意すべきでしょうか?



運用商品の選択に際しては企業年金の資産としての特性を踏まえ、老後までの長い視野を持った長期投資を心掛けることや、リスク特性が異なる金融商品への分散投資を促すなど、資産配分(アセット・アロケーション)の基礎的知識が大切です。また自らの収入・資産状況、そして経済的ニーズに合わせた運用姿勢も必要になります。



企業側の役割としては何が重要ですか?



そのために資産運用や金融商品選択に不慣れな社員・従業員に対して企業側が投資教育を充実し、資産形成を促すことが新たな従業員福祉として重要になっています。それにより、加入者が適正な資産運用や金融商品の選択ができる環境を作らなければなりません。国もこうした環境づくりを後押しするために、加入当初とその後の投資教育を法令で努力義務として定めています。



投資教育の内容としては、どのようなものが含まれるのでしょうか?



とくに投資教育の内容として、「確定拠出年金の仕組み」「老後生活設計の全体像の理解」「資産運用の基礎知識」「個別の金融商品のリスクとリターン」などを掲げ、個々の加入者の理解度に則した情報提供の工夫を促しています。このような環境のもとで、加入者である社員・従業員は運営主体が提供する株式、債券、投資信託などの中から自己責任において商品選択します。



企業側には何か義務付けられていることはありますか?



企業は3つ以上の運用商品を選択肢として提示する必要があり、そのなかの少なくとも1つは元本確保型の商品でなければならないことになっています。これにより、従業員が過度のリスクをとることから保護しています。
iDeCoの特徴と近年の発展



個人型確定拠出年金(iDeCo)について詳しく教えていただけますか?



確定拠出年金には、企業を通して加入する企業型と、個人で金融機関と契約する個人型があります。後者の個人型確定拠出年金はiDeCoの愛称で呼ばれており、勤めている企業ではなく、公的機関の国民年金基金連合会が一括して運営しています。契約した金融機関からこの連合会に資金が流れ、年金支払いなどの事務を担当することになります。



iDeCoの普及状況はどうなっていますか?



2004年に導入されてから当初は加入が伸び悩んでいたものの、2017年1月から自営業者(第1号被保険者)と民間の被用者(厚生年金加入の被保険者・第2号被保険者)に加えて、公務員と専業主婦にも加入が認められたことから、急速に加入者が増加し人気になっています。個人で契約するというだけで、後は企業型のものと同様の仕組みになります。



最近導入された「iDeCoプラス」についても教えていただけますか?



さらに2018年からは、中小事業主掛金納付制度(通称iDeCoプラス)が導入されています。対象は従業員数が100人以下で企業年金を未導入の企業です。その社員・従業員が個人型確定拠出年金に加入している場合に、労使の掛金の合計額が拠出限度枠内であることを条件として、加入者の掛金に上乗せして事業主が拠出できる仕組みです。中小企業の社員・従業員も労使合わせたトータルの掛金を自ら運用することができ、より多額の老後資金を準備することができます。iDeCoに加入しようとしている方は、是非、iDeCoプラスが利用できるかどうか、確認してみてください。



人生100年時代と言われる中で、こうした制度の重要性はますます高まりそうですね。



人生100年時代を迎えて、また公的年金の役割縮小に応じて、iDeCoやiDeCoプラスを普及させ、老後や人生後半期の生活を充実させることが望まれています。そのために、国も税の優遇措置を設けて、国民の自助努力を促しています。この税制優遇の非課税限度枠は、自営業者か被用者か、また他の年金との併用状況によって異なるので、自らしっかり確認して加入する必要があります。
iDeCoとNISAの違いと活用法



iDeCoとNISAはどのような違いがあり、どのように使い分けるべきでしょうか?



こうしたiDeCoなどが主に老後の生活を充実させる目的をもつのに対して、NISAは自身の投資目的に合わせて、優遇措置を受けて資産を形成する手段になります。iDeCoはその目的のために60歳になるまで積み立てた資金を引き出すことができません。一方NISAの資金は引出し自由です。この点に利便性があります。そもそも両者の目的が異なることをしっかり理解すべきです。



共通点もあるのでしょうか?



ただし中長期に資産を増やす目的であることや、金融商品を自ら選択すること等は同じです。とくに2023年までは、NISAにより非課税で運用できる期限が定められていましたが、新しいNISAでは期限の取り決めが無くなり、非課税期間を気にすることなく投資できるようになりました。両者は併用して活用することができますので、資金に余裕がある範囲で、目的に合わせて両者を上手く活用して欲しいものです。
長期投資を継続するためのコツ



長期投資を続けていくためのコツや心構えについて教えていただけますか?



お金を増やすことにより消費生活を楽しんだり、旅行や趣味などの娯楽に回すお金を増やすことができます。もちろん、不確実な将来に備えることも目的になります。その意味で、まずライフプランをしっかりして、お金をためることや増やすことの目標をしっかり持つべきです。将来の為と思い我慢して投資のためのお金をねん出しても、今の生活を楽しめず窮屈になったら本末転倒です。



投資における心理面のコントロールはどうすればよいでしょうか?



身構えて投資に挑む必要はありませんが、何となく余剰資金を証券会社から言われるがままに投資していると、損をした時などつい愚痴が出てしまいます。それよりも、投資の目標と投資する余剰資金の金額を事前に決めて、短期的な値上がり値下がりに一喜一憂しないことが肝要です。その意味では、敵を知って己を知れば、百戦して百勝することが良く当てはまると思います。
成功する投資のための情報収集と自己理解



投資で成功するためには、どのような情報収集が必要ですか?



関心をもって投資情報を収集し、投資対象の内容を理解することがはじめの第一歩です。投資対象には安全資産の預貯金、危険資産とされる株式投資、その中間の債券投資や投資信託があります。それぞれの資産の特徴を理解して、投資に踏み切ることが大切です。



投資における心理的要素の重要性についてはどうお考えですか?



自身の生活資金のニーズ、これからの収入と支出の他、投資には心理的要素が関わるので、心情や心理状態も影響します(専門的には、時間的視野・時間選好率やリスク態度などと呼ばれています)。自身の投資行動に向けた性向や心理状況の理解も、少なくとも悔いがない投資行動には欠くことはできません。



投資判断の基準を持つことの重要性について教えてください。



投資対象である金融商品について、客観的に判断できる軸、投資判断基準をもっておくことも大事になります。こうした軸があると、多少の損得にも動じないことになります。折角、将来を思って投資しても、値上がり値下がりが気になって仕事にも手が付かず、日常生活に支障をきたすことも、また本末転倒です。投資がストレスや家族間の諍いにならないためにも、事前の情報収集に努め、軸を決めて判断することが必要です。



投資に向いている人、向いていない人はいるのでしょうか?



逆にこうしたことが面倒で、時間を掛けることができなければ、危険資産、リスク性金融商品に手を出すことは「気」の毒になり、かえって預貯金で安全に少しずつお金を貯める方が適しています。自分自身の身の丈に合ったお金のため方、増やす方を心掛けるべきです。
投資における心理的バイアスと対処法



経験を重ねるにつれて生じる心理的な落とし穴はありますか?



一方、こうした情報収集や判断を繰り返し、慣れてきたからといって、自分が運用のセミプロになった気分になることは危険です。運用のプロや専門家でさえ、長期的に見て、市場平均以上のリターンを挙げることは難しくあります。そのために、短期的な投資成果、運用成果に一喜一憂しないことや、精神的な余裕をもつことも大切です。



行動ファイナンスの観点からはどのように説明できますか?



投資行動には合理性が要求されますが、前述したように気分や心情・感情に左右されることも多いです。最近の行動ファイナンスという研究領域では、こうした感情を上手くコントロールしながら、投資成果、運用成果を挙げる手法が研究されています。正に、己を知る部分にあたります。



過去の成功体験が投資判断に及ぼす影響について教えてください。



投資が好きであったり、得意を自認している人の多くは、過去の成功体験がそうした感情や自信過剰を引き起こしていることがあります。しかしピークのときには既に下降がみえているように、成功体験がいつまでも続くわけではありません。手痛い失敗を被ると自信喪失するのも生身の人間だからです。こうした感情の浮き沈みは、やはり精神的にマイナスでストレスにもなりかねません。自身の能力や性向を知ってこその投資活動です。
投資家によく見られる心理的特性



投資家によく見られる心理的特性としては、「ヒューリスティック」と「アンカーリング」があります。前者は、投資にかける時間が短い中で判断を下すときに、深く考えることができずに、やや短絡的に金融商品を選んでしまうことです。専門家に言われるままの投資や、マスコミやSNSで良く見聞きする評判を鵜呑みにしての投資行動です。効率的、つまり時間節約的である一方、熟慮がない分、値下がりしたり損失を被ったときに後悔は大きくなります。



そうした判断の短絡化を避けるにはどうすればよいでしょうか?



逆にそれでも構わないと思ってしまうと、平均以上の儲けを挙げることは難しくなります。事前の情報収集とそれに基づく投資判断、金融商品の選択は、後々の後悔を減らすことに役立ちます。その意味で、自身が損失を被ったときにどのくらいの痛手を受けるのかを勘案して、事前準備にかける時間を割いたら良いことになります。個々の投資家の置かれている状況、収入や資産状況、年齢や目標までの期間、そして自身の知識や経験に応じて、その程度は異なります。まずは自身を見つめ直し、己を知ることが大事になってきます。投資行動においては、クヨクヨ型とサバサバ型の性格の違いが出てきます。



アンカーリングとはどのような心理的特性なのでしょうか?



後者のアンカーリングは先入観に過度に頼ってしまうことです。こうした性向は誰でも持っているし、投資の初心者も熟練者も関係なく陥る罠です。一度の成功体験に囚われ経済環境に拘わらずに、同じ金融商品を選択し続けることが具体例になります。また一度の手痛い失敗から、当該金融商品を避け続けることも同じです。これらは、人々がもつ粘着気質に起因します。



そのような心理的特性にはどう対処すればよいのでしょうか?



もちろんこれは誰もがもつ性向であり、回避することはできません。投資行動や金融商品選択では、経済や企業活動が生き物である分、変転が激しく、状況が刻々と変わることもあります。その意味で、投資行動には時々に応じた柔軟性が必要で、少々頭が固いと積極的な投資行動には不向きかもしれません。自身の性癖を変えることはとても難しいですが、生活の習慣や環境を変えることや、また友人や同僚と話してみることで、自身の性癖に気づくこともあります。ストレスと同じで一人で抱え込むよりは、家族や友人とのちょっとした会話からヒントを得て、先入観を少しでも拭い去ることもできます。
長期投資のモチベーションを維持するコツ



長期投資を継続するためのモチベーション維持のコツはありますか?



最後に、生活資金と運用実績の見える化が大事です。そのことで成功体験を実感できることになり、長期投資へのモチベーションになります。投資の為にはまとまった資金が必要で、それを工夫して捻出することです。それには、家計簿を付けることも有効です。



家計管理についてはどのようにアドバイスをされますか?



ただ多くの人が経験しているように、家計簿を付けることは面倒くさいですし、多くの場合、長続きしません。最近は家計簿アプリが登場しだいぶ便利にはなっています。それでも長続きは容易でないですが、合理的ではない人間には、それで構わないと思います。



では家計簿はどのように活用すればよいでしょうか?



(長期)投資を思い立った当初に、家計の現状把握と大まかな未来の収支予測の意味で家計簿を付けて、毎月投資するとしたら、ないしはボーナスを投資資金に回すとしたら、どの位の金額が可能なのかの目安を付ければいいわけです。こうしたスタートアップに家計簿や家計簿アプリを利用するわけです。なかなか投資資金が増えなければ継続的に収支を見直すことになりますが、運良くロケットスタートが切れて成功体験を積み上げていけば、もう家計簿のことは忘れても良いかもしれません。いずれにしても、自身の性格に鑑みて、目標の達成まで無理なく投資意欲をもち続けられれば問題ありません。
まとめ:長期投資で成功するための心構え
本インタビューでは、東京経済大学の石田成則教授に、短期投資志向の方にこそ知ってほしい長期投資の必要性について詳しく解説していただきました。
仮想通貨投資においても、利便性の向上や取引所の安定化により、長期的な資産として見る視点が重要であることが分かります。また、iDeCoやNISAといった税制優遇制度を活用した長期的な資産形成の方法や、投資を続けていくための心理的なコツについても貴重なアドバイスをいただきました。
長期投資で成功するためには、「敵を知り己を知る」姿勢が重要です。投資対象についての情報収集と理解を深めるとともに、自分自身の投資に対する性向や心理状態を把握することで、無理なく継続できる投資習慣を身につけることができるでしょう。
今回のインタビューが、読者の皆様の資産形成の参考になれば幸いです。なお、本記事は投資助言ではありません。投資はご自身の判断と責任で行うようお願いいたします。
当サイトについて
当サイトBITNAVI(ビットナビ)は、仮想通貨や海外取引所について発信している総合情報メディアです。
仮想通貨FX歴5年以上のプロトレーダーが、海外で話題の仮想通貨や、おすすめの海外仮想通貨取引所を紹介しています。
中でも「仮想通貨海外取引所おすすめ比較ランキング」は人気の記事ですので、気になる方はぜひ参考にしてください。
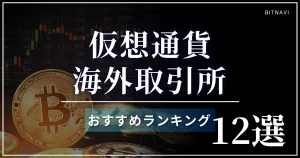
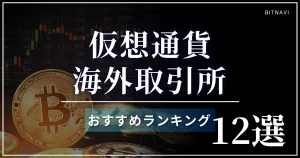
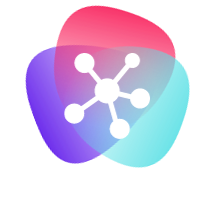
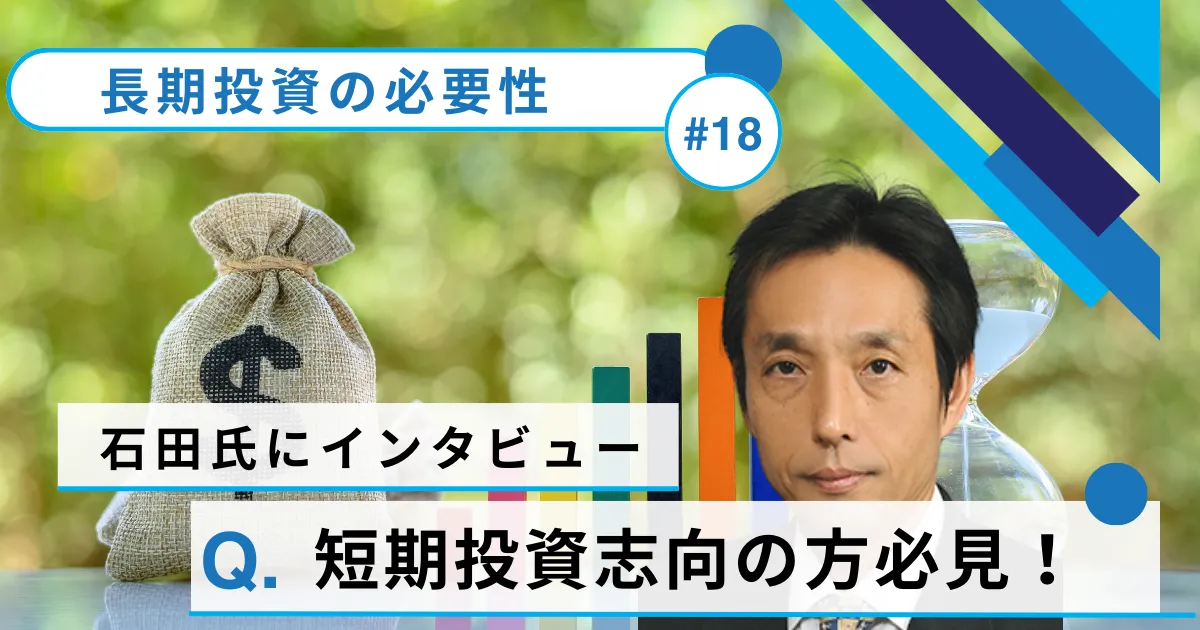

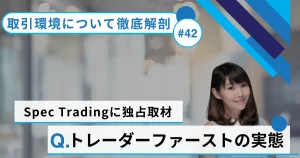

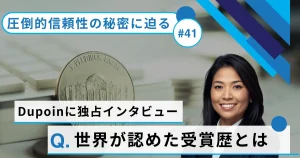

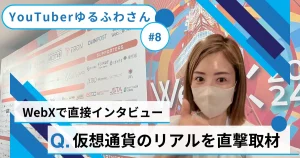
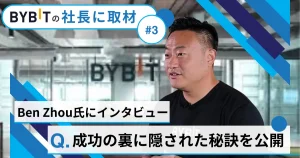
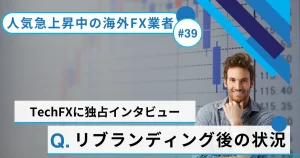
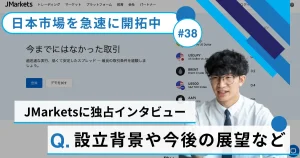
コメント